技術士にはAIと協働するマインドとスキル獲得が必須!
現在、AI(人口知能:Artificial Intelligence)、特に生成AI(Generative AI)が加速度的に進化しています。生成AIとは、「大量のデータを学習したAIモデルが、新しいデータ(文章・画像・音声・動画・プログラムコードなど)を"自動生成"する技術の総称」です。社会のあらゆる領域に浸透し、人々のくらしや社会構造を変えつつあるAIに対して、技術士はどのように対応していけばよいのでしょうか。
<AIの特徴>
・大量の知識データを学習することにより、人間の創造的活動のほとんどの領域について、人間の仕事を代替できます。
・従来のAIの機能は大量のデータの分類・判別・予測などに限定されますが、生成AIは新しいデータ(作品)を作り出す(創造する)ことができます。例えば、小説を書く、絵を描く、作曲する、映画を作る、プログラムを作ることができます。
・生成AIの創造の仕組みは人間と類似しており、次の3パターンがあります。
①学習した既存の知識を組み合わせて、新しい作品を作る。人間も同じことをしている。
➁学習した既存の知識からルール(規則・法則)を見つけて、新しい作品作る。人間も同じ。
➂知識の組み合わせと見つけたルールの両方を使って、新しい作品を作る。これが最も高度な創造。
・AIの不得意な分野:
現在の生成AIは、人間の心や倫理観の領域、即ち、個人特有の感情・思想・価値観・個性などを含む領域の取扱いは、不得意と考えられています。これらの多くは、言語化しにくい暗黙知の領域です。人間の心とは何かについて充分に解明されているとは言えない現状では当然とも言えます。例えば、輸出管理の該非判定などは、判定業務と言っても単純な分類・判別業務ではなく、新技術や輸出先の国際関係などの機微を含み、AIの不得意な分野と言えるでしょう。
<現状のAIに対する評価>
生成AIは人類にとって極めて有用なツールと考える楽観論がある一方、脅威論もあります。生成AIが従来のAI(分類・予測型AI)と異なり、人間の創造性の発揮としての創作物、即ち、小説、絵画、作曲などの完成品を、人間の作品と見分けがつかないレベルで作ってしまう能力を持ち得ること、つまり人間のライバルとなり得ることが、AI脅威論の主要な根拠ではないかと思われます。さらに、AIは人間と同様に、フェイクも作れますし、嘘もつきます(ハルシネーション)。もっとも「嘘も方便」と諺にあるように、人間社会では時には嘘も許されますが。
<AI時代の技術士のサバイバル戦略>
近い将来、AIが人間の仕事の多くを代替してしまうと予想されています。しかし、そもそもAIが人類の脅威なのか味方なのかの議論の行方も定まらない現在、AIのもたらす未来は極めて不透明であると言わざるを得ません。ただ、明確に言えることは、①AIの創造主は人間であり、➁AIが人間のスキルを劇的に拡大し、圧倒的な作業の効率化・生産性向上をもたらすツールとしての側面を持つことです。このAIのツールとしての側面と、技術士の専門家としてのスキルを合体すれば、技術士は、技術の専門家として将来も生き残っていけると考えます。
特に、該非判定などAIの不得意な分野を補完し、最終判断を技術士が行うことで、サービスの品質向上、効率化・短納期によるコストダウンなど、顧客サービス向上にも貢献することが期待されます。
そのためには、技術士はAIと協働するマインドとスキルを身につけることが必須と考えます。AIと協働するマインドとは、AIと協働するための(新しい)倫理観であり、現行の日本技術士会の「技術士倫理綱領」をブラッシュアップすることで確立できると考えます。そして、AIと協働するためのスキルとは、端的に言えば、AIに指示を与えるための言葉(「プロンプト」と呼ぶ。)を最適化する能力です。
<プロンプトとAIのイラスト作品の簡単な例>
代表的な生成AIのChatGPTに、次の2つのプロンプトを入力した時の、イラストのアウトプットを図1、2に示します。
① 生成AIの特徴を表すイラストを作成してください?
➁ 生成AIができる得意なことを表すイラストを作成してください?
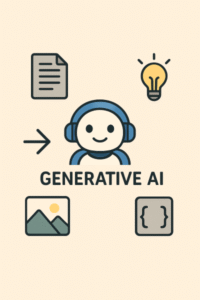
図1.生成AIの特徴を表すイラスト(キイワードがアバウト)
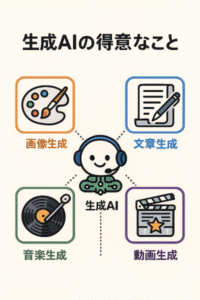
図2.生成AIができる得意なことを表すイラスト(キワードが具体的)
他にもいろいろ試して見ることにより、次のことが見えてきます。
・プロンプト次第でイラストは大きく変化する。
・同じプロンプトを入力しても、いつも同じイラストが得られるとは限らない。
・プロンプトの入力は、複数回行うなどの試行錯誤が必要。
・時々、誤字などの誤りを含むことがある。
・最終の仕上げは、人間が行うことが必要。
・AIのアウトプット(作品)案で不充分な部分について、技術士の専門性が発揮できる。
この例から、AIと協働するためには、適切なプロンプトを入力するスキルが重要であることが言えます。(技術士(情報工学)小山和夫)

